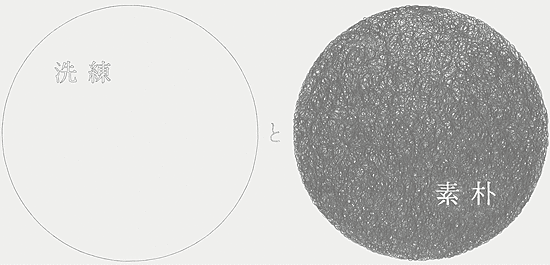
5
連続トーク「都市と地方」
串田和美(俳優、演出家、まつもと市民芸術館芸術監督、TCアルプ代表)
+ 皆川明 + 三谷龍二
三谷:
串田和美さんは俳優であり、まつもと市民芸術館の芸術監督や、いろんな場所で神出鬼没の芝居もやっていらっしゃる方です。ずっと都市で活動をされてきて、思い入れを持って地方にいらっしゃった。とはいえ串田さんですから「都市と地方」というテーマに限らず、非常におもしろい話がうかがえると思います。
皆川明さんはミナペルホネンのデザイナーで、東京に本社がありますが、この会場の目の前に小さなお店を作られたり、南三陸に工場を作られたり、地方との関わりが深く、地方に対して独特の考え方を持っていらっしゃる。そんな話も聞けたらなと思っています。
串田さんは、松本の使われなくなった保育園で公演する予定があって、そこはまつもと市民芸術館の裏側にありまして、松本の人も知らないような場所ですよね。洗練された劇場ではなくて、あえて使いにくい場所で芝居をする。それがすごくおもしろいなと思って、その話をまずお聞きしたいです。
串田:
あえて使いにくい場所で、というつもりではないんです。むしろ使いやすそうだなと思うんです。まつもと市民芸術館は立派でしょ。立派だから立派なことをしないといけない、という先入観がある。機構がそろっているので、いろんなことをやってくれるのではないかと期待されてしまう。それが電球ひとつでぽつんと座って芝居をすると、期待はずれになるでしょう。
芸術館の裏に「アルプスシャツ」という工場があるのですが、そのすぐ向こう側に保育園があって。閉めてから長いし、雨漏りもするし、もうすぐ壊すんだそうです。僕らが芝居をやるのは、そこの子ども用の体育館。先日行ってみたら、けっこう天井が高くて、斜めになっていて、おもしろい空間でした。僕が思っていたより広かった。いろんな部屋があって、のぞくと埃だらけで、子ども用のいろんなものが積んであって。トイレなんかものすごく小さい。小さい子のトイレって、上から先生が「大丈夫?」と見ることができるようになっている。そういうのを見てジーンとしたりしました。僕にとっては、ある意味ではやりやすい場所かもしれません。
僕はもともと演劇人として20代の頃、六本木のガラス屋さんの地下に、そうですね、奥行はこんなにないかもしれない、天井もこんなものだったような気がする。4間の6間、その裏にちょっとしたスペースがあるくらいの小さな小さな地下劇場というものを作りました。まだアンダーグラウンドという言葉があまり普及していない頃でしたが、その自前の小さな劇場に「アンダーグラウンドシアター自由劇場」とつけました。
そのちょっとあとくらいに新宿に「アンダーグラウンドさそり座」というものを作った人がいて、その2つから「アングラ」といわれるようになった。アンダーグラウンドと最初につけた自分たちの演劇は、その後「アングラ」といわれるようになった芝居とは少しちがうような気がして、途中から「オンシアター自由劇場」と改名しました。
そこは使いにくいなんてもんじゃない。道具を入れるのも、転換するのも大変。でも、不便に対して不便と言ってはだめだ、という思いもあって、そりゃあいろんな工夫をしました。それが結果的には自分の創作の基盤になった。僕は俳優学校を出て、すぐに劇団を作って、先輩や師匠がいなかったもので、不便さからいろいろなものを学んだなと思います。設備が全部そろっているところではやれないことがある。そういう体験をずっとしてきた。だから今回の保育園跡地での公演は、楽しみで楽しみでしょうがないんです。
三谷:
皆川さんの南三陸の工場は、どんな感じですか。
皆川:
みなさんご存知のとおり、南三陸は震災でかなり打撃を受けて、女性が働く場所が足りないということで、僕らが少し関わらせていただきました。洋服を作るのは、ミシンがあればできるという、個人でコンパクトにはじめられる職業です。工場を作れば、目の前の仕事に集中しつつ、必然的に人が集まってコミュニケーションが取れるので、いいのではないかと思いました。
それで建築家の中村好文さんに工場を建てていただいて、僕らが仕事をお願いして縫っていただく。1年半くらい経ったと思うんですが、みなさんご主人が漁業をされているのを手伝いながらの仕事なので、好きな時にできるように、という感じです。
三谷:
この場所10cmも、たまたま見つけて、どうしたら生かせるかなと考えてはじめたわけです。大きなきっかけがあったわけではない。でもはじめると広がっていく感じがあります。
皆川:
きっかけは小さくても、そこから想像することによって、いくらでも広がると思います。
三谷:
串田さんも前からアジトみたいなものが好きだとおっしゃっていて、小さい場所はいろいろ想像できる部分がありますね。
串田:
そうですね。おふたりの感覚に近いこともあるし、やっていることがちがうので、当然ちがうところもあります。おふたりは古いものをサッと直して、ヒュッと洗練させてしまうじゃないですか。僕はそのままが良い、とか。演劇を作っているので、そこに住むわけではないですから。
日本は、さっさと壊してしまう文化ですよね。昔から、障子でも何でも、さっさと変えたり壊してしまう。ヨーロッパだと何世紀も壊さない。その跡地を劇場にしたりするので、その形跡が明らかに残っていて、それだけでワクワクする。ロンドンの「ファイヤーファイターステーションシアター」は、本当に消防自動車が入っていたんだなと感じられます。
時々行くシビウという、歌舞伎がきっかけで仲良くなって、僕もそこで演出したことのあるルーマニアの地方都市があります。そこには映画館を改造した「ラドゥスタンカ」という劇場があって、国から助成金がおりて、堂々とナショナルシアターと名乗っています。
大きな芝居をやるには、共産圏時代の古めかしい倉庫を劇場に仕立てて使います。もともとが劇場じゃないから使いにくいんだけど、入っただけで「わあ、いいなあ」とドキドキする。何かの跡というものに、すごく惹かれますね。
南アフリカに「マーケットシアター」という円形劇場があります。なぜ円形かというと、その昔は奴隷市場だったのだそうです。その後、野菜などの競りのマーケットになり、アパルトヘイトがあって、演劇のための劇場になっていって、僕が行った時は黒人たちがブレヒトの「セチュアンの善人」を楽しそうにやっていました。かつてここで白人が奴隷を買ったと聞くと暗い気持ちになるけど、彼らはむしろそこで明るく伸び伸びとお芝居をしている。古い建物にはいろいろな歴史の情景が残っているから、それはそれでそのままにしておいた方がいいのではないか、という気持ちになります。
皆川:
僕の松本の店はもともと薬局だったので、薬の棚がそのままあります。僕も最初あそこを見たとき、折角あるものを壊し過ぎないように、どこを直してどこを直さないのかをよく考えました。直し過ぎると折角の記憶が消えてしまう。ものには記憶が入っているから、なるべく残しておきたいけど、自分たちが思うような形に直して使っていく。それを串田さんは演劇という形で埋めているんだと思います。
串田:
そうですね。その埋め方がお互い少しちがうところがおもしろいですね。
三谷:
「洗練と素朴」というテーマですが、技術を向上していこうとか、上手くなりたいと思うと洗練の方に行きやすいんだけど、失うものがある。だから立ち返る必要があるのかもしれない。そこにあるアフリカの椅子から受け取れるものは、たくさんありますよね。
串田:
時間が経つと変わるものもある。たとえばラーメン屋さんによくあったようなパイプ椅子で、当時は「ちょっとそれは」と思っていたものが、20年30年経つとおしゃれに思えてくる。今、まわりにあまりないから。「ちょっとちがうんだよね」と思っていたものが、「良いね」と思えるようになるって何だろう、おもしろいですね。
三谷:
串田さんの芝居を観ていると、すごく自由というか、台本を追っかけている感じはなくて、どこから見ても楽しいというのを大事にしていらっしゃる。それは僕たちが背負っている「こうしなきゃいけない」を壊しながら作っているからだと思うのですが。
串田:
確かに「こうしなきゃ」とは意識していないです。「決まりがあるの?」と、反発したくなる感じはいつもあります。習性なのかな。そうしないとものが作れないと思っています。
たとえば、先日シェイクスピアの「テンペスト」をやった。かつて地球の反対側でシェイクスピアが作った時はそうだったろうけど、今は400年後だし、日本だし。今の時代なんだから、どう作り直していったらいいのか考えて、最初は壊すことからはじめる。壊さないと新しく生まれない。まあ、大変な作業ですが、大変な分、楽しいです。
三谷:
稽古中もどんどん変わっていくと聞きました。
串田:
ええ、もちろん。今度作る「或いは、テネシーワルツ」というお芝居は、加藤直さんという演出も兼ねている方が本をくださって、僕のことをわかっているから「こういうふうに完成してほしい」という戯曲じゃないんです。時々セリフが入っているけど、どこまでがト書きなのか、感想文なのか、あるいは作家の願いなのかわからない。
僕はそれをまず丸暗記してやるのではなく、その時、頭に浮かんだことを即興でどんどん演じていって、次のものに発展させるという作業を何度も繰り返していく。まだ固まっていないんですが、多分その場所に入ったら、またいろいろ変わると思います。そういう作業を繰り返しているうちに、その時々の外的刺激、たとえばイライラするような嫌な事件やニュース、逆に思いがけないうれしいことも、悲しいことも、その時のさまざまなことに影響を受けながら、その時の舞台を作っていく。まあ、作品によっていろんな作り方をしますが、今回の「或いは、テネシーワルツ」は、そんな風に作っています。
僕は古い戯曲だとしても、ゼロから作った本だとしても、芝居は筋を観るものじゃないと思っています。音楽のように、そこ向けてぼんやり風が吹いていることを受け止めるようなもの。言葉ではなかなか上手く伝えられないんですけど。
一番の理想は、夕焼けをずっと見て気がついたら2時間経ってしまった、とか。川の流れをボーっと見ていたらすごく泣けてきた、とか。
そういうものでありたいと思っている。そんなのは理想の理想で、遠いところにあるんですけど、心の中にそういう理想がある。ですから、観てくださる方は感じるとおりに笑ってくださったらいいし、にらんでいる人がいても、しかめっつらしている人がいてもいい。そういうのがおもしろいと思う。
ある年配の人は「シェイクスピアの難しいのは困るよ」と言う。でも、小中学生の兄弟が身を乗り出してずっと観続けている。「おもしろかった」と言って、次の日にまた来た小学生がいる。子どもがあんなに興味をもって観ているのに、どうして大人には難しいんだろう?
わかりたい人、わからないと落ち着かない人というのは、たくさんいる。わかるということは、わかった気になるということ。「あー、なるほど」と思っても、全然ちがうかもしれない。難しく考える人がいて、理屈をつけて解説する人がいる。それを否定はしないけど、人それぞれ自由なものでありたいな、と思うんです。
皆川:
夕焼けを見る2時間と、演劇を観る2時間。演劇は場面が変わったり、活発な感じがありますが。
串田:
夕焼けも活発なんです。自分の感情を引き出してくれるものじゃないですか。だから見ていられる。活発という言い方をしましたが、「うわ、逆転した!」とか、「え? なんだろう」とか思ったりすること、そういう感じかな。
三谷:
改めて「都市と地方」というテーマですが、僕は「開く」、あるいは「閉じる」ということをときどき考えています。ものを作るのは「閉じる」感じがある。閉じないと良いものが作れなくて、良いものを作れれば、逆にそれを届けるために「開く」ことが必要になる。
地方の人たちは、外へ、都会へという意識が強いけど、むしろ閉じて時間をかけて作ったものの方が広がっていく感じがするんです。たとえば松本でおもしろい店を作った人が、都会に出て店を出して広げていこうとする。自己拡大欲なのだと思うんですけど、そうじゃなくて、もっと自分の中に入っていって質を高めれば、遠くからでも来てくれるだろうと思うんです。
良い芝居があれば遠くからでも観に来てくれるだろうし、そういう地方のあり方がおもしろいと思うんですよね。
串田:
演劇は東京じゃないとできないと思っている人や、まずは東京に行って修業をする、と思っている人はたくさんいます。東京という都市文化は、地方の人がやってきて作っている。
大昔ですが、東京生まれじゃない人が、東京生まれの人を少し馬鹿にして言うんです。「あいつは坊ちゃん、俺たちは雑草だ」って。嫌な思いをしました。
バブルの時代、僕は渋谷の東急文化村という大きな施設で芸術監督をやって、演劇の世界もすごいことになっていって、限界を感じたんです。文化村の仕事が終わった1996年に「東京じゃないところは、どうだろう」と地方の可能性を、ふと思った。
それで15年前、松本から声をかけていただいた。先日亡くなった前市長の有賀さんが「これを作ろう、あれを作ろう」と美術館を作り、芸術館を作った。強引だったから反対運動もあって大変な騒ぎになった。僕は呼ばれて来たのに反対されるという(笑)。
三谷:
「反対する人は関心がある人だ」とおっしゃっていましたね。
串田:
そうなんですよ。地方にはかわいそうな劇場がいっぱいあって、「前にお芝居やったのはいつですか」と聞くと、「1年近く前だね」となる。「今は何やっているの」と聞くと、「卒業式と、成人式と、宝くじの発表」と。「ええっ?!」となる(笑)。劇場は立派なんですよ。でもこんなに立派である必要のないことばかりやっている。
そういう劇場施設を作るときに漠然と「良いんじゃない」という人や、「面倒臭いから黙っていよう」という人ばかりで、ちゃんとした意見を言う人がいなかったんだろうなと感じます。
でも、松本はみなさん熱心だった。反対する人がたくさんいて、僕もしょっちゅう膝を突き合わせて話をした。ただ反対ということではなく、「やるならこうでしょ」とか「こういう劇場がいい」とか、いろんな意見の人がいたと気がつきました。
三谷:
それをいろいろ細かく意見を聞いてまわったんですね。
串田:
そうですね。しょっちゅう集会に呼び出されたり。80回とか。おっかない顔している人もいた。
三谷:
最初はかなり険悪な雰囲気でしたよね。
串田:
そうそう。いろいろ話をしているうちに、つまらないこと言う人がいると今度はそっち同士で議論になったりして「いいぞ、いいぞ」と(笑)。そういう感じから3、4年はかかったかな。反対していた人が、今ではたくさん応援してくれています。
三谷:
演劇を観る地元のお客さんが増えていますね。
串田:
でも、さっき言ったように、まだ「難しい」と言う人もいる。世の中だって難しいのに生きているんだから、お芝居はこの面倒な世の中に比べたら、そんなに難しくないということを伝えたいなと思います。
お芝居は、毎日身体を使って1、2カ月かけて作ります。松本で感じたのは、劇場の中だけでなく、街にいる人とも作っているんだということ。誰もが自覚があるわけではないけど、社会と演劇の関係を学んだというか、発見したことはたくさんありました。
皆川:
「空中キャバレー」の入り口でお店をやるというのは、そういうこともあるんですね。
串田:
「空中キャバレー」という、音楽とサーカスとお芝居のごちゃ混ぜのものをやっています。舞台のすぐ横の空間に、街の人に有志でお店を出してもらって、休憩時間にそこで飲んだり食べたり、演者がおもしろいことをやったりする。
座席が決まっていなくて、場内の席が動くから、車椅子の人や、子どもは転んだら大変だとか、僕らも気を使うんですが、お客さんがいろいろ協力してくれる。みんなで一緒に作っている感じですね。
三谷:
串田さんは芝居を作るということだけではなくて、街との関わり、TCアルプのような自前劇団の活動など、演劇と関わりのある全体を作っている感じがありますよね。
串田:
去年、屋外に舞台を作って芝居をやりました。音は筒抜けで、隙間からのぞけるような、本当に素朴で、まるで中世の絵に出てくるような舞台でした。夕焼けになってカラスが飛んで、すごく素敵なんだけど、時々焼き芋屋も通るし、良いセリフの時にピーポーピーポーが重なって「いつまでも鳴らすなよ」と思うけど、それも風情があるなと思える。
もちろん入場料を払ってもらわないと困るんだけど、たまたまそこを通った人が「何だか不思議な音がしていたな」と思う。そういうことも演劇の一面だと思いました。
三谷:
いろいろな雑音が入ったり、突然雨が降ったりすると、普通は演劇空間が邪魔される感じがしますよね。
串田:
そうですね。クラッシックコンサートで、咳をした人がいただけで機嫌悪くなっちゃうとか、まだ拍手しちゃいけないんじゃないかとか、聴衆の方もくたくたになっちゃうじゃないですか。
坂本龍一さんが芸術館の大ホールで演奏していた時、良いところで小さな子どもがフギャーと声をあげた。すかさず彼は「良い間だね」と言った。大した人だなと思いました。そういうふうにどんなことも取り入れてしまう。だって予測しないことが起こるんだからしょうがない。
信濃毎日新聞の新社屋ビルの建設予定地で「遥かなるブルレスケ」というお芝居をやりました。最後の日は、途中で雨かなと思いつつ、雲がなくなってホッとして芝居を始めたら、途中からザーッと降ってきた。一応お客さんには透明のカッパを配っていたけど、カッパなんか着たら雨の音がバタバタ跳ね返る音で、セリフも何も聞こえやしない。
会場:(笑)
串田:
こっちは芝居を辞めるわけにいかないから、もうヤケになってびしょ濡れで演じていたら、舞台監督が飛び込んで来て「ここでちょっと幕を降ろします」と言った。僕は「え、ここで止めるか?」と思って、客席に向かって「みんなどうする!?」と聞いたら、みんなが「やれーっ!」と言って、土砂降りの中でとんでもない公演になった。お客さんたちにとっても僕たちにとっても、そんな舞台は二度とないから、今だに語り草になっていて、その日そこに居合わせた人たちは得意そうに言います。「あれは最高の芝居だった」って。
三谷:
工芸はパフォーマンスとはちがって、完成したものをお客さんに出すので、そこが全然ちがうんですよね。
串田:
でも工芸の、特に陶器なんて、使っているうちに割れてしまうこともあるじゃないですか。割れてしまったことに対して「だから作っているんです」と言う人がいて、ちょっとうれしかったりしましたね。
皆川:
木を彫っていると節が出てきたりして、結果それが景色になったりしますよね。焼きものもきっとそうだと思うんですけど、そのハプニングを景色とみるか、欠点と見るかという心持ちでずいぶんちがってきますね。
三谷:
瞬間的にどうしようと判断する。そういうことはいつでもやっていますね。ただし、ひとりで、ですけど。
皆川:
節が出たから不良品だ、ではなく。
三谷:
変えていきます。
串田:
計画どおりじゃなくて、手なのか道具なのかわからないけど、そっちへ導いてしまうということはありますよね。
三谷:
漆はわりとそうで、毎回ちがうやり方をしてしまうんです。塗り方にもいろんなやり方があるなと、やりながら考えている。しばらくすると忘れてしまって、やっているうちに思い出す、ということを繰り返しやっています。
串田:
忘れるって、すごく大事ですよね。意識的に忘れちゃうんですけど。「お芝居って、どうやって作るんだっけ?」と思うことがしょっちゅうあります。
会場:(笑)
三谷:
僕らはもの1個1個を見ることが多いんですけど、たとえばこういうふうに展示した時に、会場に入った瞬間に感じる全体の空気感はすごく大事だなと思っているんです。
串田:
ものすごく大事ですね。入った時に始まっているし、気配で「これ、おもしろいな」とか「駄目だな」とか、最初にわかってしまうことはよくある。
皆川:
劇場だと、劇を観る前提で行くけれど、そこが保育園だと何が起こるかわからないから、頭がニュートラルな状態で入り込めるんでしょうね。串田さんが最初にやりやすい、とおっしゃったのは、そうことですか。
串田:
そうです。そういうニュートラルな環境を既成の劇場の中に作ろうとするとけっこう大変なんです。作れないことはないかもしれないけど、ものすごく工夫とお金がかかる。
三谷:
地方に住んでいて芝居を観に行くと、良いなと思うことがあります。仕事をしたあとの火照りを残したまま15分くらいで芝居の中に身を置ける。日常と非日常が身体の中でつながっている感じがあって、それがすごく心地良い。都会だと、電車に乗って……となるから、途中で自分の日常の熱が消えてしまう気がします。
皆川:
僕、先週初めてニューヨークへ行きましたけど、メトロポリタン入って、コム・デ・ギャルソン展をやっていて、アービング・ペンをやっていて。出た途端、目の前にピカソの絵があって、それはまさに都市ならではの独特な空気感でした。
串田:
東京にいると情報を集めるのに良いんだよ、と言う人はいます。そのとおりなんだけど、いっぱい人の名前や情報を知っているのと、感動することはちがう。知っているということと、感じているということは、ちがうと思うんです。東京でも感じることはもちろん可能だし、そういう人はたくさんいるけど、雑音のない地方の街のほうが感じやすいし、純粋に感じようとする人が多いような気がします。
松本はすごい街なんですよ。冬に稽古をしていて、いつも通る高砂町の路地に道路工事のおっちゃんがいて、「寒いね」とか「今日はあったかくて良かったね」とか声をかけているうちに、向こうからも話かけてくれるようになった。公演日が迫ってきて、ある日「忙しいんですか」なんて言うから「そうなんだよ」って答えたら、「シェイクスピアですか」って。
会場:(笑)
串田:
「え?!すごいな」と感動しちゃったね。東京の工事現場の人には絶対言われないぞと思って。「この人招待しようかな」って。
会場:(笑)
串田:
それだけで、ものすごくうれしかったなあ。それだけで生きている気持ちがする。そういうものの宝庫です。恥ずかしがり屋の人も多いけど、自転車ですれちがったら「やあ」って言ってくださいね。すごいうれしい。
会場:(笑)
三谷:
この後、松本でいろいろな計画をお持ちだと。学校みたいなものを考えていらっしゃる?
串田:
そうですね。今年は「空中キャバレー」を7月の終わりから10日間くらいやります。それから学校というか、「シアターキャット」というワークショップをやります。それから東京の文化村シアターコクーンでチェーホフ作品をやるんですけど、それをこっちにも12月あたまに持って来る。それから「白い病気」という反戦劇なんですが、昔カレル・チャペックが書いたものを少し直してやろうと。そして来年、1年おきにやっている歌舞伎を作ってこっちにもってきます。いつもより1カ月早くて、東京が5月、松本が6月。
次々やるし、カンパニーの連中も自分たちの芝居をやるし、ぜひ来てください。お芝居は苦手なんだよなと思っている人も、「へーっ」と思ってくださると思います。
皆川:
「空中キャバレー」をご覧になったことがある方、いらっしゃいますか。僕は最初に観ておもしろくて、続けて2回観て。観終わると2年後が楽しみで。会場に入る時から始まっているんです。
三谷:
お芝居であり、コンサートのようであり、サーカスのようであり。それが切れ目なく混じり合っているんですよね。
串田:
日本でキャバレーというと、おっちゃんがお姉ちゃんと遊ぶところというイメージがあって、最初は「え!キャバレー?」と言う人もいた。ヨーロッパでは、キャバレー文化というものがあったんですね。芸術家や小説家や絵描き、みんながそこに可能性を感じていた。それまでアカデミックだった芸術に限界を感じた人たちが目を向けた動きです。フランス・パリではじまって、ベルリンにも広まっていって。
演劇のテーマがあって、ストーリーを追って、というものではなく、時間と空間をみんなで共有しながらも、いろいろひっくり返っていて何が起きるかわからない、というようなものを作りたいな、とずっと思い続けています。ご期待ください。
三谷:
楽しいというのはすごく大事なことなので、そこは工芸も見習いたいと思っています。ものを通じて楽しんでもらう。小さい幸せかもしれないけど、それは瞬間的に伝わるものだし、広がっていくものだと思う。どういう素材で、どういう技術を使ってという説明的な事柄だけではなく、感じてもらうのがすごく大事で、直観的に伝えていくことを自分でもやっていかなきゃいけないと思っています。
串田:
僕が演劇をやっている若い人から感じるのは、演劇を演劇からしか学んでいない、ということ。僕は美術、音楽、工芸だとか、そういうものからたくさん学んだ。工芸もきっとそうだと思う。ただ工房の中でやるのではなく、外の空気を吸って、何かを見て、誰かに会って、感覚をふくらましていくものだと思う。そういう交流がもっとあれば良いと思うし、松本はそういう可能性がすごくある街です。お芝居を観なくても芸術館にフラッと来ても良いし、そういう場所がいくつも増えると良いなと思います。
展覧会の記録
・山本忠臣(ギャラリーやまほん)
・菅野康晴(工芸青花)
・三谷龍二(10cm)
・猿山修(さる山)
・森岡督行(森岡書店)
・小林和人(Roudabout/OUTBOUND)
・皆川明(ミナ ペルホネン)
連続トークショー
5
「都市と地方」 串田和美 + 皆川明 + 三谷龍二
1
2
3
4
5
「都市と地方」
串田和美 + 皆川明 + 三谷龍二
©2018 ROKKU CRAFT STREET