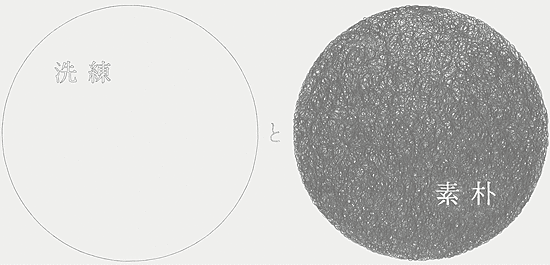
1
連続トーク「洗練と素朴」
分藤大翼(信州大学 准教授)+ 三谷龍二 + 皆川明 司会:菅野康晴
三谷:
連続トークショーの第1回は、「洗練と素朴」というテーマです。全体のメインテーマでもあります。工芸に携わる人は、腕を磨くことで技術を洗練させ、素材もできるだけ洗練させようと考えます。しかし単に上手というだけでは、なかなか人の心を打つものができない。うまさではない形を考えると、素朴というのか、土に根を張ったような感じが必要になる。工芸では、洗練と素朴を行ったり来たりしているところがあるんですね。
そんなテーマで、みなさんがどう考えているか、ものとして出してもらうとおもしろいんじゃないかと思いました。展示を見ると、いろんなものがあって、コメントもなかなかおもしろいです。展示もトークも1回きりですが、ホームページを作ったので、そこで少しずつ取り上げていきますので、ぜひご覧ください。
菅野:
今回のチラシのデザインは、ミナペルホネンで作っていただきました。イラストとキャッチコピーがとても印象的ですが、皆川さんから「洗練と素朴」というテーマについて、そしてイラストについて、お話しいただけますか。
皆川:
今回の「洗練と素朴」というテーマを聞いたとき、あの白い丸と黒い影のようなものが頭に浮かびました。対比しつつ、同一性をもっているイメージです。文字はタイポグラフィーのようですが、手書きしました。「洗練」を自分なりに解釈して、できるだけ細い線できれいな円と文字を書いて、「素朴」は、鉛筆でグリグリッとやりながら、余白として残しながら文字にしました。
紙は、素材感で「素朴」を表したいと思って新聞紙のようなクラフトペーパーを選びました。うっすらと折り目がありますが、じつは印刷で影を入れています。
三谷:
ああ、それは知らなかった。
菅野:
「洗練と素朴」は対照的な概念でありながら、同一性も感じるとおっしゃっていましたが、それは、どういうところですか。
皆川:
自分で図案を描くときに「洗練と素朴」という言葉を意識して絵を描いたり、ものを作ることはないんですが、洗練は瞬間のひらめきのようなもので、素朴は経験から湧き出るもの。作業をしているときは、どちらも両方が出ていると思います。これは洗練、これは素朴と言い切れない、ひとつに含まれている感じ。そこにたどり着くのが、ものを作るときの着地点なのかなと思います。
三谷:
僕が木の器を作り始めたころ、木の器というと厚ぼったくて野暮ったいものが多くて、どうしても素朴な感じがしがちでした。それだとほかの陶磁器やガラスとの釣り合いが悪く、今の生活で使っていただくには、もう少しシャープにモダンにしなきゃいけないと思って、洗練させることに傾いたんです。
でも、それを木という素材が戻してくれるというか、ノミを使って彫ると、どうやっても素朴に引っ張られる。その行きつ戻りつみたいなところが今でもあります。洗練に寄っている器もあれば、素朴に寄り過ぎている器もある。自分のなかでバランスを取りつつ、両方混在していると感じています。
菅野:
では分藤さん、自己紹介と、おふたりの仕事についてコメントいただけますか。
分藤:
その前に、皆川さんにちょっとお聞きしたいのですが。この「洗練と素朴」のデザインで、「と」が細かな点で描かれていることについて教えてください
会場:(「本当だ」とざわつく)
皆川:
よくそこを見てくださったと思います。今回のテーマの「洗練と素朴」はそれぞれ分けられるものではなく、別々に語りながら結局同じところに向かっていくイメージで、「&」とは言い切れない曖昧な、完全に物質化していないイメージがあったんです。なので、文字は白と黒、「&」はつぶつぶの粒子で描き分けました。
分藤:
洗練、素朴、それぞれとてもいい言葉だと思うんですが、今回のテーマのミソは「と」じゃないかなと僕は思っています。「と」は、とてもおもしろい言葉で、ものを分けると同時につなげる役割を果たしている。「と」があるのがいいな、というのが今回のテーマに対する僕の感想です。
こちらにいらっしゃるおふたりに比べるとまったく無名なので、ちょっと自己紹介しますと、松本にある信州大学に勤めている教員で、専門は人類学です。20年ほど前からアフリカのカメルーンという国に通って、熱帯雨林に暮らす狩猟採集民の文化を調査研究しています。
僕たち人類はこの地に誕生して以来、99%ぐらいの期間ずーっと狩猟採集民だったんです。人類のもっとも基本的で、もっとも長続きしている生き方で、今でもそれを色濃く残している人たちがアフリカの森にいることを知って、ぜひ彼らに会いたいと思ったのが、僕がアフリカでの調査研究を始めた動機です。
三谷さんから、今回こういう企画があるので来てみないかというメールをいただいて、テーマが「洗練と素朴」だと聞いたとき、アフリカの森に暮らす彼らの文化を端的に表現すると、ひょっとしたら「洗練と素朴」になるのかもしれないという直感が働きました。そこで、僕がアフリカで経験してきたことをお話しすればいいのであればお受けしますとお返事しました。
ともあれ、この場においては、僕は「と」の役割を果たすつもりでいますので、こちらのおふたり「と」皆さんをつなぐ役回りで、つぶつぶの状態でここに座っていられればいいなと思っています。
菅野:
ありがとうございます。分藤さんが三谷さんと皆川さんの仕事を「洗練と素朴」というテーマで語るとしたら、どうなりますか。
分藤:
えっと、それはちょっと下手なことを言えないので、話を変えていいですか?
会場:(笑)
分藤:
展示がほんとに楽しくて、目利きという言い方はいやらしいかもしれませんが、ものを愛する人たちが「洗練と素朴」というテーマでお選びになったものが並んでいるので、おふたりに選んだものについて、まずはお話しいただけるといいなと思います。
三谷:
窓際にある藁は、知り合いの方にお願いして持ってきてもらいました。形や使い勝手はもちろん大事ですが、僕らはテクスチャというか素材感にまず惹かれるんですね。素材には素朴という要素が入っていて、ただ積んであるだけの藁から、すごく感じるものがある。ものづくりはそういうところから出発することが意外と大きいんじゃないかと思います。
藁馬は新潟県で昔から作られているものですが、まず砧で叩いてやわらかくして藁を曲がりやすくするとか、工夫がある。長い時間をかけた、この素材とのつき合いのなかででき上がってきた形だと思うんです。
織物のひとつは「からむし」というイラクサ科の多年草を素材とした布です。今日も来ていらっしゃいますが、奥会津の昭和村には、からむしの栽培から始めて、布を作っている方たちがいます。そこは昔から上質なからむしが作られてきたところで、昭和村のからむしの繊維は越後に出荷されて、越後上布とか小千谷縮が織られてきました。
一番奥の束ねてあるのが、からむしの繊維です。あれだけでも十分にきれいですが、さらに糸にするには、長い時間と手の洗練が必要です。日本の織物は非常に手間ひまかけて作られてきたものですから、機械生産や海外生産で安くなって、手で織るのは難しくなったと思うんです。
世界でも他にないような布を、どうやったら残せるのか。みんなで考えていらっしゃるし、僕も少しでもお手伝いができればと思っています。昭和村へは分藤さんも行って、フィルムを作っているんですよね。
分藤:
はい。僕はこれまでアフリカで記録映画を作ってきたのですが、その経験を活かして、昭和村で、からむし文化を対象とした記録映画を製作しています。
三谷:
その隣は、伝統的なものではないんですが、奈良県の方の布です。ご自分で畑に種を蒔いて綿花を栽培して、綿を紡いで1本の糸にして、縦糸を絹、横糸を綿にして織る。そうやって手をかけないと出ない風合いがあって、それを大事にしていらっしゃる。
今の時代に、栽培から始めて糸を作るというのは、経済的にはかなり難しいところがあると思うんですが、その方が織る布はとても洗練されていて、ぜひ残していきたいと思っています。
皆川:
僕は、島根県石見地方のお面と、イタリアの刃物メーカーの貝殻型ナイフと、しょうぶ学園の方の陶器のオブジェを選びました。あと、軽井沢の辺りで工房を構えていらっしゃる小山剛さんの木の作品と、熊谷幸治さんの小さな土器。熊谷さんは去年のトークに参加されましたが、驚くほど小さい作品です。あとはモリソン小林さんの鉄のオブジェです。
石見のお面は、和紙を貼る前の状態です。とっても美しいシェイプで、新幹線の先頭の代わりになるのじゃないかと思うくらい無駄のないカーブを持っています。長年作り続けられてきて、時の経過でだんだん洗練されてきたけれど、もともとの素朴さは残っていて、それがいいなあと思いました。
「G.Lorenzi」はイタリアの刃物メーカーで、ロレンツィ家の人たちがいろんな刃物をデザインしています。この小さなナイフは、僕は普段キャンプなんかでチーズを切るために使っていますが、貝の形は手にしっくり馴染んで、刃を収納すると役割もちゃんと果たしています。まさに「洗練と素朴」をあわせもった形だと思います。
しょうぶ学園では……そもそも障害者という言い方に僕は代わりの言葉を見つけなければと思うんですが、今はわかりやすく一般的に使われている言葉を使うと、障害者の方たちが焼きものや和紙や木工の工房で作品を作っています。自由な作品づくりというのはなかなか難しくて、作り手として普段から葛藤しているところがあるのですが、この作品は自由が妨げられずにそのまま形になっている美しさがあって、喜びが湧くように感じます。
熊谷さんは、普段はその土地の土を使って大きな土器を焼く方ですが、新しい展示を拝見したら、とても小さな作品を作っていました。彼が持っている手の力を強く感じて、「洗練と素朴」という今回のテーマに沿っているなと思いました。
モリソンさんは山に登って、そこで見た景色を鉄で表現しています。あの作品の裏には、どの山のどの辺りと書いてあるんです。熊谷さんと重なる部分あるかもしれませんが、超技巧的な手先によって、自分の体験や植物への思いを表現している。そこに「洗練と素朴」というテーマがあるなと思いました。
菅野:
皆川さんのセレクトは「洗練と素朴」を兼ね備えたもの、ということですね。
皆川:
そうですね。テーマを聞いた当初は、僕のなかでは「洗練」と「素朴」だったんですが、考えていくうちに、ひとつのなかにあるという結論になりました。
菅野:
三谷さんは、皆川さんのセレクトをご覧になって、どうですか。
三谷:
刃物がおもしろいなと思ったんですよ。皆川さんが選ぶものはいつも、僕たちが思う形とはちょっとちがう。熊谷君のああいう作品を僕は知らなかったんです。もっと素朴な、その風体も野焼きしているような、いかにも土器っていう感じの人ですけれど。
会場:(笑)
三谷:
あんな繊細なものもやっているのだなと思って。でも熊谷君の作品全体を見ると、確かにその繊細さは出ていますよね。さすがに美術大学を出ている人だなという感じがしました。縄文の原始的なエネルギーに満ちた部分と、都市で育った人間だから都市的なものも自分のなかにある。両方出てくるのが、今の作家のおもしろいところだと思います。
分藤:
おふたりは作り手として、自分のなかに「洗練と素朴」を常に意識されているのでしょうか。三谷さんからは先ほど、自分の創作における「洗練と素朴」の話をいただきましたが、皆川さんご自身のなかでは「洗練と素朴」は、どういう感じになっているのでしょうか。
皆川:
洋服づくりは分業で行なっていて、人の分業であり、機械との分業もある仕事です。僕がプランするときには、機械がどのくらい素朴に動けるかを考えます。素朴とは、不完全を美しさや存在感につなげていくことだと思いますが、機械がやるにしても人がやるにしても、最終的な形に向かうプロセスのなかに、できるだけ多く素朴を入れることを考えるのが、デザイナーの仕事だと思っています。ひとりでは完結しない仕事なので、それをなるべくまわりに伝えることを普段から心がけています。
分藤:
三谷さんも最後の仕上げはご自身でやって、その手前のプロセスは職人さんたちと一緒にやるんですよね。
三谷:
ものから離れてデザインする部分と、作る部分と、両方あるのが自分の仕事のやり方としてちょうどいいと感じています。工芸でそういうやり方をする人は少ないんですが、少し人の手を借りたほうが使いやすいものになると僕は思う。作家の思いが強く出すぎると使いにくくて、そこを抜くために分業制をとっています。そもそも日本の工芸は分業でやってきた場合が多い。作品ではなく生活品なので、そうなったんだろうとは思います。
分藤:
三谷さんのものづくりでは、作り手である自分が作りたいものを作るだけだけはなく、使い手としての使い心地を丹念に探りながら、ものの形を整えていくわけですよね。作り手と使い手をつなぐ意識も大事にされている。
三谷:
そうですね。ちょっと前まで、作家性をつなげるために、作家は自分が作ることが大事だったと思うんです。それはおそらく西洋的な考え方で、表現とか個性とか新しいものとか、今まで見たことないようなものを作るのが作家という存在だった。でも工芸のなかにはそうじゃないものがあるのではないかと考えて、普通に使えるものを作っていったわけです。
それから、家のなかはずいぶん洋になったのに、食器だけが和だという違和感があって、その調整もあったと思います。たとえば産地の人たちは技術があってどんどん作るんですが、使う人からは「今はこういうの、あんまり使わないよね」という声が聞こえてくる。でも問屋制があって、作り手との間にいろんな人が関わってくると、その声が作り手につながっていかなかった。
だからクラフトフェアもそうですけども、僕たちは直接お客さんと会って、使う側の声を直接聞きながら、自分でもどういうものが欲しいかを考える。人の欲しいものはわかりにくいので、結局は自分が欲しいものを作っていくことで、使う側と作る側の思いを混ぜ合わせる。和洋を混ぜたり、作る側と使う側を混ぜたり、そういう思考を僕たちはやってきた。そういうことができるようになった時代だったと思うんです。
あとは一次、二次産業で生産する人より、三次産業のサービスする人が増えて、消費する人が増えたわけです。消費者の「こんなのが欲しい」という思いに生産者は引っ張られるようになっていったということも関係あるかもしれません。
分藤:
皆川さんは、自分が作ったものを使う方のことは、どう意識されているのでしょうか。
皆川:
女性の服が中心なので、自分から少し離れた存在として作っていますが、流行からではなく、どうしたら気持ちいいかなと着る人のメンタリティから考えます。このくらいのボリュームのスカートだったら、こんなドレープが広がるかな。足さばきがこう流れてきたら気持ちがいいだろうな。ポケットはこの位置でこの深さだったらちょうどいいだろうな。そうするとこんな仕草が生まれるだろうな。そんなシュミレーションをかなりします。
こんな人に着てもらいたいというミューズのような存在は持たず、自分のこういう記憶をグラフィックにして布に乗せよう、こういう心地良さや質感を素材感として乗せようと考えて、そこに共感してくれる人が着てくれたらいいなと思っています。
三谷:
皆川さんの服は、トンがったファッションとはちがって、手仕事の味わいに近い。そこがおそらくみなさんの気持ちにつながっていくんだと思うんです。
皆川:
ファッションの流行という、大勢の人が良いと思うものが良いものとされる状態が、パーソナリティを表現する者として疑問でした。なので自分は、情報ではなく、自分が実際に感じた思いを素直に表現すれば、共感してくれる人がいるかもしれない。そこが服づくりのスタートでした。人を驚かせるというよりは、共感してもらう部分を表現したかった。
三谷:
自分の感じていることを素直にやるのは、なかなか難しいことですよね。それを自由にしてしまうことが大事だと思うんですが。
たとえば木だったら、使っているとだんだんゆがんだり、シミができやすいから、上から塗装するのが普通です。でも自分はこの感じが好きだから塗らない、とか。たとえば漆は、だいたい決まったやり方があるんですが、僕は自分の好きな方法でやっちゃう、とか。本場の産地でそんな仕事をしたら、同業者に馬鹿にされます。そういうプレッシャーがあるけど、自分の感じていることを素直にやっちゃう、それが大事だと思います。
皆川:
素直に出そうという思いもありますが、理論的に、自分が作れる洋服の数はこのぐらいで、共感者がその分だけいれば成り立つ、とも考えられます。何百万人、何千万人との共感がなくても、自分をありのままに出して共感してくれる人が、これくらいはいるだろうという仮定で作ってもいいんじゃないかと思います。
三谷:
人の欲しいものはわかりにくいけど、自分の欲しいものはわかる。自分が作れる範囲で作って、共感してくれる人がいて、その人が気持ちがいいと言ってくれたら、自分が作る意味もあるかなと思いますね。
分藤:
三谷さんの作品は彫り跡がはっきりと残っていて、手の動きが使う人に伝わります。皆川さんの作る服は、機械を使っているけど、人の手を介した表情があります。
手は、僕たちが一番共感しやすい部分で、手から表情を読み取るセンスが僕たちにはある。だからおふたりの作るものからは、手仕事に対する共感が生まれるのではないかと思います。
今回、三谷さんが選んだ布や、ミナペルホネンの服は、完成されたものを見ると、とても洗練されていて、その手前の素朴な作業はちょっと想像しにくいのですが、現地で作っている様子を見れば、素朴な作業の積み重ねという側面もあるんだろうと思います。
昭和村では、7月から8月にかけて、からむしの刈り取りと繊維を取り出す作業がおこなわれます。家々の戸口のところで、女性の方々が「からむし引き」という作業をします。それは素朴な作業のように見えて、とても洗練されたもので、だからといって、そんなに難しいわけではなく。やはり、生活の中にあるものづくりは洗練と素朴が同居している感じになるんだろうと思います。
布を見てそこまで想像することは、普通はなかなかできないんですが、こういう展示を通じて、でき上がる前の状態や、手仕事のプロセスを知ってもらうことによって、共感を越えた理解を得て、相応の価値が認められることにもつながればと思います。
菅野:
分藤さんはこのトークのために、ものを持ってきてくれました。
分藤:
アフリカの森に暮らす狩猟採集民の暮らしぶりから、僕が「洗練と素朴」を感じるものをひとつ持ってきました。これは、ナッツや葉っぱをすり潰すために使う調理道具のひとつなのですが。
この板の方は、アフリカンパドックという木の皮の部分です。ただの木の皮です。しかも剥いだのではなく、剥げ落ちていたものを拾ってきたのだと聞いています。そして、すり潰すための球状のものですが、こちらはつる性植物の実です。持ってみると、ちょうど手におさまるサイズで作業がしやすい。ただ、やっぱり拾ってきたものを、そのまま使っているだけです。
まさに素朴で、あるがままのものを拾ってきて、あるがままに使っている。ここに洗練を見てとるのは難しいように思われますが、僕は彼らの「これでいいのだ」という判断力に「洗練」を感じます。つまり無駄なことをやらない。使い手として、ものについてあれこれ考えない。そのセンスは長年の暮らしの中で洗練されてきたものだと思います。
彼らは本当にがんばらない人たちで、意匠を凝らすということをしない。「これでいい」と思えばそれまでで、それ以上のことはしないんです。これは、彼らの生活が何千年、何万年と続いてきた秘訣なのではないかと思います。
僕はものの大切さを考えるうえで、10年20年ではなく、100年200年、あるいは1000年2000年ぐらいで考えることが大事だと思いはじめています。皆川さんがミナペルホネンを少なくとも100年は続けたいと言うことが、僕はすごくよくわかるし、大事なことだと思います。からむしに関わる文化に興味があるのも、縄文時代の昔から人々が手がけてきた経緯があるからです。1000年が難しければ、せめて100年ぐらいで捉えて、今できることをやる。そのうえでものの価値を考えてみることが大事なんじゃないかなあと、思っています。
三谷:
「これでいいのだ」っていう感じは、僕が出品したボーエ・モーエンセンの椅子も同じなんです。戦後のデンマークで、より多くの人に、より安く、丈夫な椅子を、と依頼されて作った椅子ですが、確かに普段使いの庶民の椅子として「これでいいのだ」っていう感じがあります。手に入れてからも何10年も経っていますが、使うたびに気持ちがいい。
これ以降のモダンデザインの椅子は、いろんな素材でいろんなことをやっています。もっと装飾をつけることはできるし、もっと手を加えることもできるけど、デザインにおいて「ここでやめる」って大事なこと。まっすぐな棒にして、ペーパーコードを編むことで強度を増して、使い込んだ素材感もすごくいいし、まさに「洗練と素朴」だなと思います。
分藤:
「これでいいのだ」という判断は洗練から生まれるもので、その手前には、使い心地や使い勝手の面で「これでいいのか」という素朴な問いの積み重ねがあるということは、つけ加えておかなければいけませんね。
三谷:
そうそう。
菅野:
アフリカの人々も、そうした問いを発してるのでしょうか。
分藤:
僕が学んでいる人たちは、その問いが希薄なんですよ。
会場:(笑)
分藤:
そこはおもしろいところで、「これでいいのか」と散々問わないと「これでいいのだ」とは言えないのが私たちの社会です。それに対して彼らの社会は「これでいいのだ」と思えば、それで十分で、小さな失敗を繰り返したり、多少は他人に迷惑をかけつつも、自分の生活を維持でるんです。
菅野:
このトークの前に分藤さんとお話ししましたが、アフリカの人たちには「洗練と素朴」という概念はまずないとのことでした。
分藤:
アフリカでも身分の格差があるような社会では、たとえば貢ぎものや供えものなどには洗練されていることを良しとする文化があります。けれども、僕が学んでいる狩猟採集社会は格差のない平等社会なんです。おそらく、そのことと関わって「洗練」や「素朴」にあたる言葉がないのではないかと思います。彼らはものを判断するとき、優劣ではなく、それがその時、自分にとっていいものか、そうでないか、を基準にしているんです。
菅野:
他人の評価は気にしていない。
分藤:
そうですね、気にしている様子がありません。そういえば三谷さんは「これいいよね」って言い方をよくしますよね。
会場:(笑)
分藤:
そのシンプルな言い方がアフリカの森で暮らす人たちに通じるなと。
会場:(笑)
三谷:
確かに「これでいいのか」って、いつも考えています。自分で作るだけだったらいいけれど、人に買って使っていただくとすると、強度の問題であるとか、手の触った感じや、素材感の経年変化とか、いろんなことが想定できるので、いいのか悪いのか考えます。そのうえで「これでいいのだ」と言えるものが作りたいですね。余計な心配もあるかもしれないので、そんなことは考えないという姿勢も大事にしたいです。
分藤:
彼らがものごとの良し悪しを厳しく問わないでも生きていられるのは、暮らし自体がしっかりしているから。熱帯雨林という豊かな自然と共生することで、食べることには困らないというベースがあるからなんです。僕たちの暮らしは、食べることも含めて、これ大丈夫なんだろうかと思うことが多いじゃないですか。もちろん、人とものとの関りは大事だけど、そのことを暮らしのなかにどう位置づけるのか、長い目で見てどのような関係が望ましいのかを考えることが大事だと思います。
皆川さんが近い将来の夢として宿泊施設を考えていらっしゃることについては、いかがですか。
皆川:
先ほど言ったように、流行からものを作ることに疑問があって、それとはちがう価値の領域があることを立証したいしたいという欲求があります。
宿については、おもてなしやサービスが良いとか、設えが高級であるとか、そういう判断基準になっていることが不思議だなあと思って、果たして滞在することの喜びは、その良し悪し次第なのだろうか。滞在するという能動的な喜びが生まれることも大事なことなんじゃないかと思ったんです。ビジネスとしてではなく、価値のベクトルがひとつに行き過ぎているものに対して、ちがう方向を考えてみたいという興味があるんです。
三谷:
旅館は、なかなかいいのがない印象があります。豪華に煌びやかにすれば人は喜ぶだろうという勘ちがいをしている旅館が多いですね。
分藤:
サービスが過剰になっているという側面があって、こうすれば気分がいいでしょう、こうすれば居心地がいいでしょうと、まあ一方的に、そこに滞在する人に向けてサービスを提供する傾向が強いですよね。でも本来は、もてなす側ともてなされる側とのやり取りのなかで、お互いにとっていい形を探っていくという、ちょっと面倒くさいかもしれないけども、そのコミュニケーションのなかでお互いにとっていい形を探ってみようという試みが必要なのではないかと思います。宿泊施設を考えるうえでも、さっき能動的という言葉が出ましたが、宿泊する側も積極的にそこに滞在することに関わって、受け入れる側はそれをサポートするような形のホスピタリティ、サービスではなくてホスピタリティのほうが大事だということになりますね。
会場から:
質問ではないんですが、私は「洗練と素朴」という言葉をうかがったとき、まさに日本の伝統文化そのものだと思いました。日本の文化は平安時代の古典文学から、能や芭蕉、いろんな系譜でつながってきましたが、表に現れるもののなかに、ものの哀れとか幽玄とか、侘び寂びとか、目に見えない部分も含みながら延々と続いてきたと思います。私はその目に見えない部分を「素朴」と捉えました。
たとえば利休が「待庵(たいあん)」でしたか、最終的に二畳の茶室を作りましたが、あれを素朴という意識だけで作ったら、とても人の心は動かせないと思うんですが、、いろんな対象を見てきて、身につけてきた利休という目利きが、洗練という目をもって削ぎ落していった、そこに美が確立したと思うんです。
素朴を簡素とか、ちがう言葉で置き変えられると思いますが、洗練と素朴、このふたつは分けられない日本の伝統的な様式だなと思いました。どうも失礼しました。
三谷:
割り茶になる前は、もうちょっとエンターテインメントで華やかで、人を集めた宴会のようだったと思うんですが、日本の場合は洗練していくと侘びというか素朴のほうに行く。豪華なほうに行かないんですよね。旅館もそっちに行って欲しいんですが。日本の伝統を考えれば、そうになっていくんだろうなという気はします。
分藤:
じゃあ僕から質問を。皆川さんは若い頃から海外に行って、いろんなものの影響を受けながら仕事されてきました。三谷さんは最近、海外で作品を見てもらう機会が増えました。日本の文化という話が出ましたが、日本と海外という観点から、ご自分の作品や仕事について思うところはありますか。
皆川:
ヨーロッパで展示会をすると、僕らが作った洋服を見て「日本的な服だ」と言われることが多いんです。日本発祥ではない洋服を、もともと発祥した文化圏で見せたときにそう言われるのが、とてもおもしろいと思います。自分たちの暮らしや文化を、知らないうちに洋服に落とし込んでいるのだなと感じます。
僕が服づくりをはじめた頃は、女性の服の価値観として、簡単にいうとセクシーな服を求められたんです。でも僕はそこに価値を見出していないので、自分のスタイルで作り続けてきたら、今では自分たちの服がヨーロッパでも受け入れられるようになりました。
三谷:
日本の布の作り方って、ものづくりの背景にある空気感とか自然を大事にするところがありますね。西洋は外に対象化するけれど、日本は自分の内側に呼び込むところがあると思う。そういう感覚はなかなか西洋に伝わりにくいと思うんですが、素材に対する浸透するようなこの感じは悪くないので、海外の人たちにも伝わればいいなと思います。近代を和らげるような力があったらいいなと思っています。日本の工芸は西洋のものに比べて自然を内に含んでいる部分が大きいと思う。なぜそういうものを僕たちが作るのかを伝えていければいいかなと思います。
展覧会の記録
・山本忠臣(ギャラリーやまほん)
・菅野康晴(工芸青花)
・三谷龍二(10cm)
・猿山修(さる山)
・森岡督行(森岡書店)
・小林和人(Roudabout/OUTBOUND)
・皆川明(ミナ ペルホネン)
連続トークショー
1
「洗練と素朴」 分藤大翼 + 三谷龍二 + 皆川明
1
「洗練と素朴」
分藤大翼 + 三谷龍二 + 皆川明
2
3
4
5
©2018 ROKKU CRAFT STREET